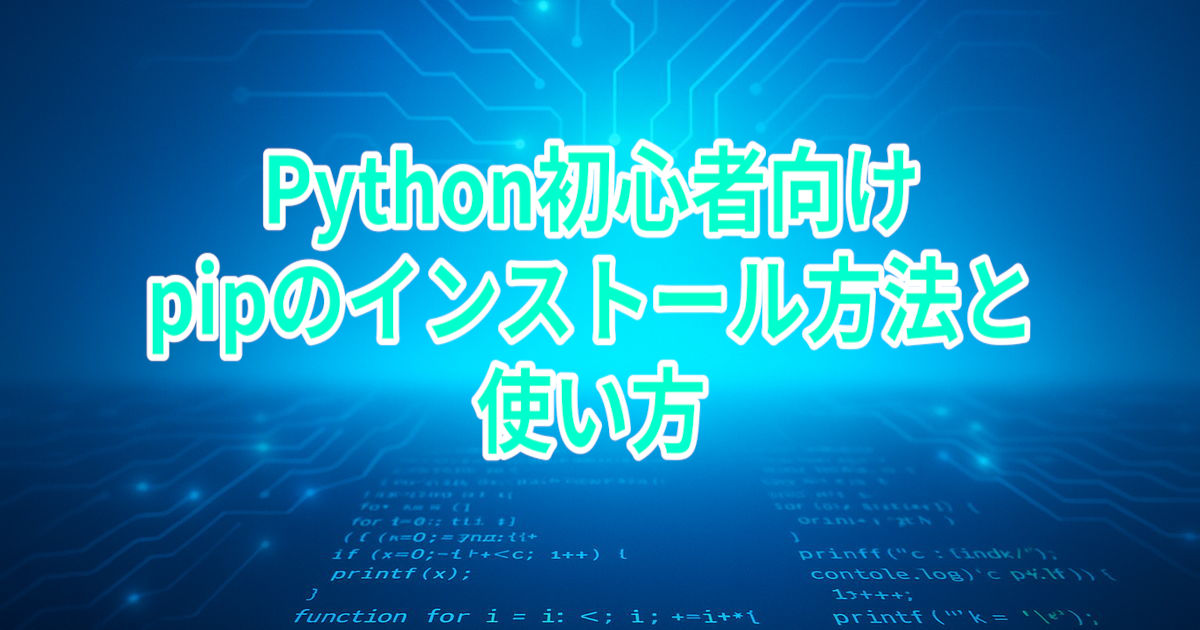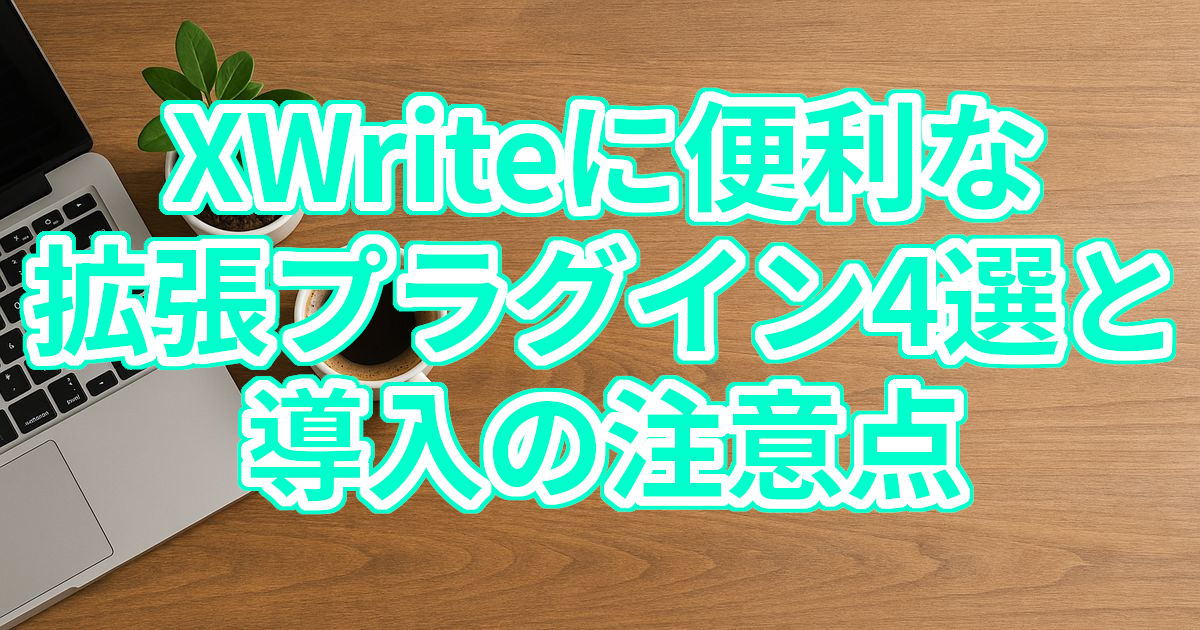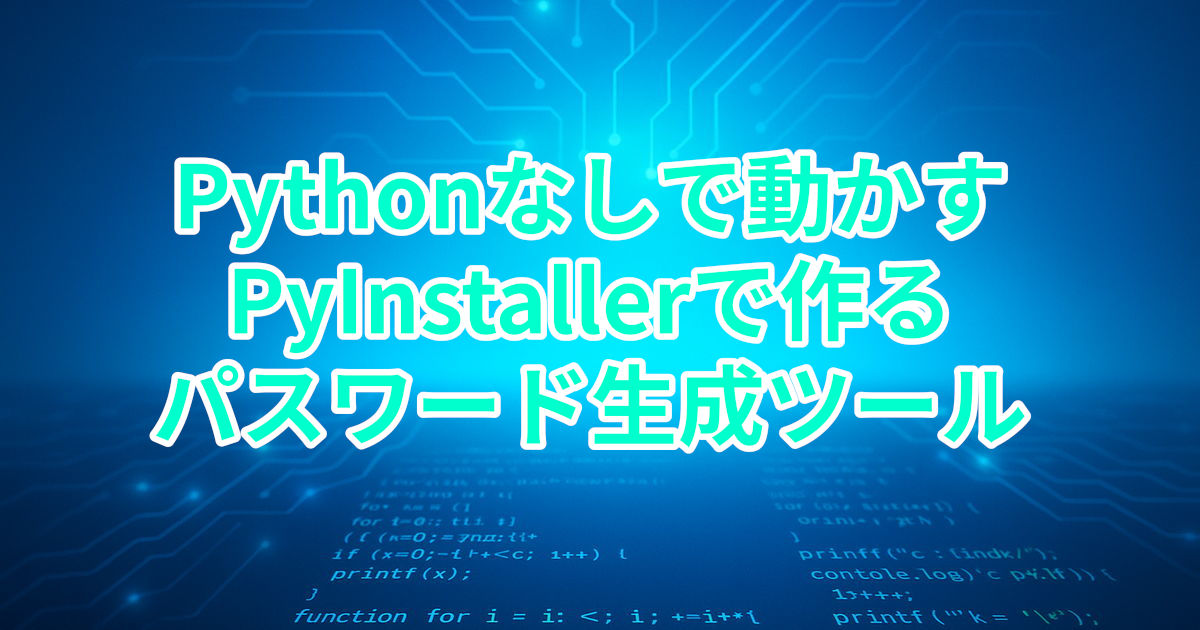Pythonをインストールしたけれど「ライブラリの追加がよく分からない」と感じる方は多いと思います。
私も最初は同じように戸惑いました。
Pythonは標準機能だけでも便利ですが、pipを使えば外部ライブラリを簡単に追加でき、使える機能が大きく広がります。
pipでインストールしたライブラリはimport文を使って呼び出します。
VSCodeで環境を整えていれば、すぐに試せるのが魅力です。
最初は覚えることが多く感じるかもしれませんが、慣れてくると効率化やツール開発にも役立ちます。
この記事ではpipの基本的な使い方から、代表的なライブラリの導入例、import文の解説、さらに仮想環境venvについても紹介します。
この記事で分かること
pipとは?Pythonに機能を追加する仕組み
pipはPythonのパッケージ管理ツールです。
インターネット上で公開されているライブラリを簡単にインストールできる仕組みで、Pythonを拡張するための標準的な方法になっています。
たとえばWebサイトにアクセスする機能や、データを見やすく整形する機能など、pipを使えば数行のコマンドで追加できます。
Pythonにとってpipは「機能を増やす入口」と考えると分かりやすいです。
私の考えとしては、pipを理解することがPython活用の第一歩です。
最初はややとっつきにくいですが、ライブラリを追加して実際に動かしてみると「Pythonって本当に便利だ」と実感できます。
pipの確認とインストール方法
Pythonをインストールすると、多くの場合はpipも一緒に入っています。
まずはターミナルやコマンドプロンプトを開いて、次のコマンドを入力してみましょう。
pip --versionバージョン番号が表示されればpipは利用可能です。
もし「コマンドが見つからない」と出た場合は、Pythonのインストールパスが通っていない可能性があります。
その場合は再インストールや環境変数の設定を確認してください。
pipのバージョンが古いと新しいライブラリが正しくインストールできないことがあります。
その際は次のコマンドでアップデートを行います。
python -m pip install --upgrade pipこれで最新のpipを利用できるようになります。
pipはライブラリ管理の要になるため、まずはここをしっかり整えておくと安心です。
ライブラリをインストールして使ってみる
では実際にライブラリをインストールしてみましょう。
今回は軽量で分かりやすい「emoji」ライブラリを例に使います。
インストール
ターミナルで次のコマンドを入力します。
pip install emoji数秒でインストールが完了するはずです。
ライブラリによってはサイズが大きく時間がかかるものもありますが、emojiは非常に軽量なので初心者の学習に向いています。
importして使う
次に、Pythonのコードからemojiを呼び出してみます。
import emoji
# 絵文字コードを変換
print(emoji.emojize("Python is :thumbs_up:"))
# 絵文字を含む文字列をそのまま表示
print("Hello World 🌍🐍")実行結果
Pythonのコードをファイルに保存してから実行します。
Python is 👍
Hello World 🌍🐍たった数行で文字列に絵文字を表示できました。
これならPythonの初心者でも成果を実感しやすいと思います。
私の考えとしては、最初に触れるライブラリは「分かりやすい成果があるもの」が良いです。
難しい数値計算やデータ処理のライブラリから入ると理解が追いつかずに挫折しがちです。
emojiのようにすぐ試せて楽しいライブラリは、学習の入り口にとても向いています。
import文の使い方
pipでライブラリをインストールしても、Pythonコードの中で呼び出さなければ使えません。
ここで使うのが「import文」です。
基本の書き方
もっともシンプルな方法は次の形です。
import ライブラリ名mathライブラリをインポートしてコードを書いた例は次のとおりです。
import math
print(math.sqrt(16)) # 4.0 と表示エイリアス(別名)の指定
ライブラリ名が長い場合は、別名をつけるとコードが読みやすくなります。
import numpy as npこのように書くと、以降は np という短い名前で利用できます。
部分的なインポート
ライブラリの一部だけを取り込むことも可能です。
from math import sqrt
print(sqrt(25)) # 5.0 と表示VSCodeでPythonを実行する環境を整えていれば、これらのimport文はすぐに試すことができます。
VSCodeであれば、予測変換を行う機能があるため、コードの途中まで書くと入力する候補を表示してくれるので表示に便利です。
私も最初は「書き方が多くて覚えるのが大変」と感じましたが、実際にコードを書いてみると自然に慣れていきました。
import文はPythonを扱う上で欠かせない仕組みなので、手を動かしながら覚えていくのがおすすめです。
pipでよく使うコマンド一覧
pipにはインストール以外にも便利なコマンドがあります。
ここでは代表的なものを紹介します。
インストール
pip install ライブラリ名指定したライブラリをインストールします。
アンインストール
pip uninstall ライブラリ名不要になったライブラリを削除します。
インストール済みライブラリの確認
pip list現在インストールされているライブラリを一覧表示します。
バージョン指定インストール
pip install ライブラリ名==1.2.3特定のバージョンを指定してインストールできます。
私の考えとしては、初心者のうちは「install」「uninstall」「list」の3つだけ覚えれば十分です。
細かいオプションは使いながら少しずつ理解していけば大丈夫です。
上級者向け:venv(仮想環境)の使い方
pipは便利ですが、1つの環境にすべてのライブラリをインストールすると管理が複雑になります。
そこで登場するのが仮想環境(venv)です。
プロジェクトごとに専用の環境を用意できるため、異なるバージョンのライブラリを同時に扱うことが可能です。
仮想環境を作成する
次のコマンドで「myenv」という仮想環境を作成できます。
python -m venv myenv仮想環境を有効化する
作成した仮想環境を有効化するには以下を実行します。
Windowsの場合:
myenv\Scripts\activatemacOS / Linuxの場合:
source myenv/bin/activate有効化すると、ターミナルに (myenv) のような表示が出ます。
この状態でpipを実行すると、仮想環境内にライブラリがインストールされます。
仮想環境を無効化する
作業が終わったら次のコマンドで仮想環境を終了できます。
deactivate私の考えとしては、最初はグローバル環境にpipでインストールしても問題ありません。
しかし、プロジェクトを複数扱うようになるとvenvの重要性が見えてきます。
早いうちに仕組みだけでも理解しておくと後々のトラブルを避けられるでしょう。
まとめ
この記事ではpipの基本的な使い方から、軽量ライブラリ「emoji」の導入例、import文の書き方、便利なpipコマンド、さらに上級者向けに仮想環境venvを紹介しました。
pipを使えばPythonに新しい機能を簡単に追加して、import文と組み合わせることで、すぐにプログラムで使うことができます。
最初は操作やコマンドを覚えるのが大変ですが、慣れるとPythonの力を大きく広げられます。
私もpipを使い始めたことで、学習だけでなく効率化や自作ツール開発につなげることができています。
今後、pipで導入したライブラリを活用して便利な自動化スクリプトを作る方法も紹介予定です。